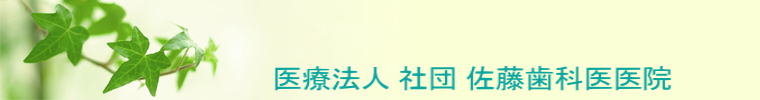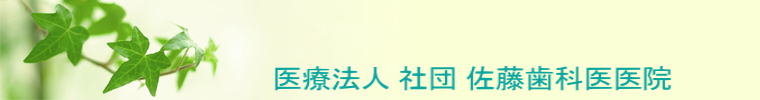| 用語の説明(歯周病) |
 プラーク,歯垢(しこう) プラーク,歯垢(しこう)
プラークとは、歯垢・細菌性プラーク・デンタルプラークなどとも呼ばれています。歯や義歯・冠・
ブリッジなど固形の構造物に付着又は固着した細菌集団です。細菌の他に細菌産生物や剥離した上皮細胞・
好中球(白血球の構成成分)などを含みます。歯肉の上にある歯肉縁上プラークと、歯肉の下に有る 歯肉縁下
プラークに分類され、1立方ミリメートルのプラーク中には10の8乗個程の細菌が含まれて居り、歯周病やウ蝕の
原因細菌が含まれている。バイオフイルムという菌体外多糖類から構成されるグリコカリックスに覆われ、
内部の細菌は共生・共存して好中球などの食作用と各種抗菌薬の浸透を防いでいる。ですから、TVで宣伝し
ているウガイ液で99%以上の細菌が死滅するというのは誤りです。正しく言えば「浮游している細菌の99%以上を
死滅させる」で、機械的にバイオフイルムを破壊してから補助に使うというなら意味があります。
 プラーク・コントロール・レコード(PCR) プラーク・コントロール・レコード(PCR)
歯に付着するプラークの率を表す。現在日本の厚労省ではオレリーの表を用いております。歯の表面に付着するプラ
ークを近心・遠心・頬側・舌側(口蓋側)の4面で検査して付着していると1点.とカウントし、付着していた歯面数(点数)
÷残存歯数÷4面×100でパーセントを計算します。
PCRが20%以下にならないと、歯周病の進行は止まらないとされ、以前は手術が出来ませんでした。実際に歯肉剥
離掻爬術(FOP)をして効果を出すには15%以下にしておく必要が有ると思います。
 ポケット・プロービング・デプス チャート) ポケット・プロービング・デプス チャート)
歯に付着している歯肉との間にある、歯肉溝の深さを測定します。
中央部で1ミリまで歯間部で2ミリまであれば、健康であるとされます。
3ミリまではOKという歯科医もいますが、当院では中央部の3ミリは問題視しています。4ミリ・5ミリは中等度の歯周病
と判断し、6ミリ以上は重度の歯周病と診断します。
頬側3点、舌側(口蓋側)3点の一歯に付き6点を測定するのが基本です。(6点法といいます)
 BOP(歯周検査時出血率) Bleedinng On Plobinng BOP(歯周検査時出血率) Bleedinng On Plobinng
歯周ポケットの深さを測定することは重要な臨床検査ですが、その際に測定した部位からの出血はそこに炎症があ
ることを意味します。臨床では非常に重視される数値です。
出血部位数÷歯数÷6×100で数値化します。歯周病学会では10%以下が望ましいとされています。当院では5%
以下を目標値としています。3%以下の患者さんの歯肉は綺麗です。
 動揺度 動揺度
歯をピンセットや指で揺すって動くかどうかを一本毎に診査します。健康であれば動きませんが、歯周病で歯槽骨が
吸収すると動きやすくなります。動く度合いにより0.5・1・2・3度と診断します。重度になると上下に動きだします。
 根分岐部病変 根分岐部病変
奥歯(大臼歯)は復根歯と言って根が3本又は3本(4本)有りますが、歯周病が高度に進行すると歯槽骨が吸収して
根の股の部分が出てきますが、その様な事態になると更にその部位が磨きにくくなり病状が更に悪化していきます。
また、上顎の小臼歯は歯の間の部分の形態が凹んでいる事が多く、その部位は細菌がたまり易くなりマイナス要因
となります。
 歯槽骨吸収 歯槽骨吸収
歯周病が進行すると歯槽骨の吸収が起こります。吸収のパターンには水平的吸収と垂直的吸収があり、文字どうり
に水平に減るのと漏斗状に根の周りが吸収するパターンが有ります。
吸収度合いで軽度(30%未満)、中等度(30%から50%未満)、重度(50%超)と分類します。
歯周病の進行度は歯槽骨の吸収レベルと、歯周ポケットの深さで決定されます。
 歯肉炎 歯肉炎
歯肉の炎症だけで歯槽骨の吸収は無い状態です。発赤と腫脹が見られます。発赤は細菌性の炎症に抗するために
毛細血管が増えますが、血管内の赤血球が透けて見えるから赤味が増すと教わりました。腫脹は細菌と戦うために
血管内の免疫グロブリンを含む血漿が血管から組織内へと出て行くために脹れ上がると教わりました。
 軽度歯周炎 軽度歯周炎
ポケットは3ミリまでで、歯槽骨の吸収は歯根長の30%以内
 中等度歯周炎 中等度歯周炎
ポケットが4・5ミリ有り、歯槽骨の吸収が30%を超えて50%未満の所が見られる
 重度歯周炎 重度歯周炎
ポケットは6ミリを超え、歯槽骨吸収も50%を超えるレベル
|
|
|
|
|